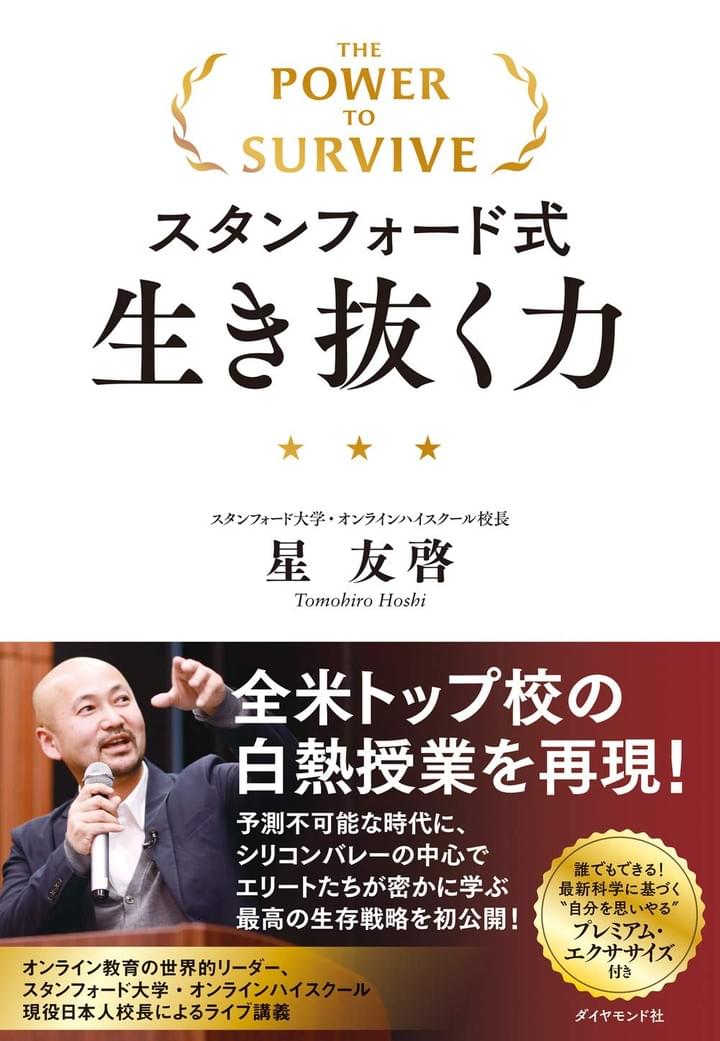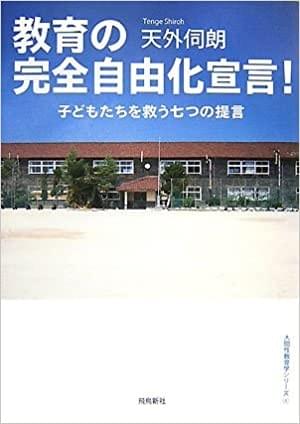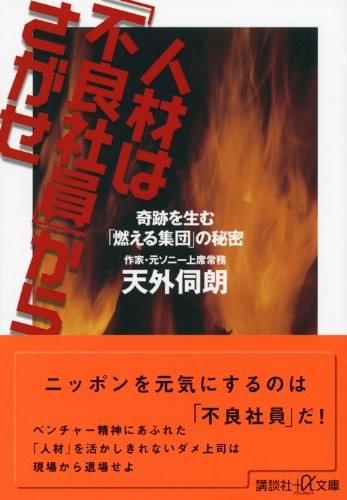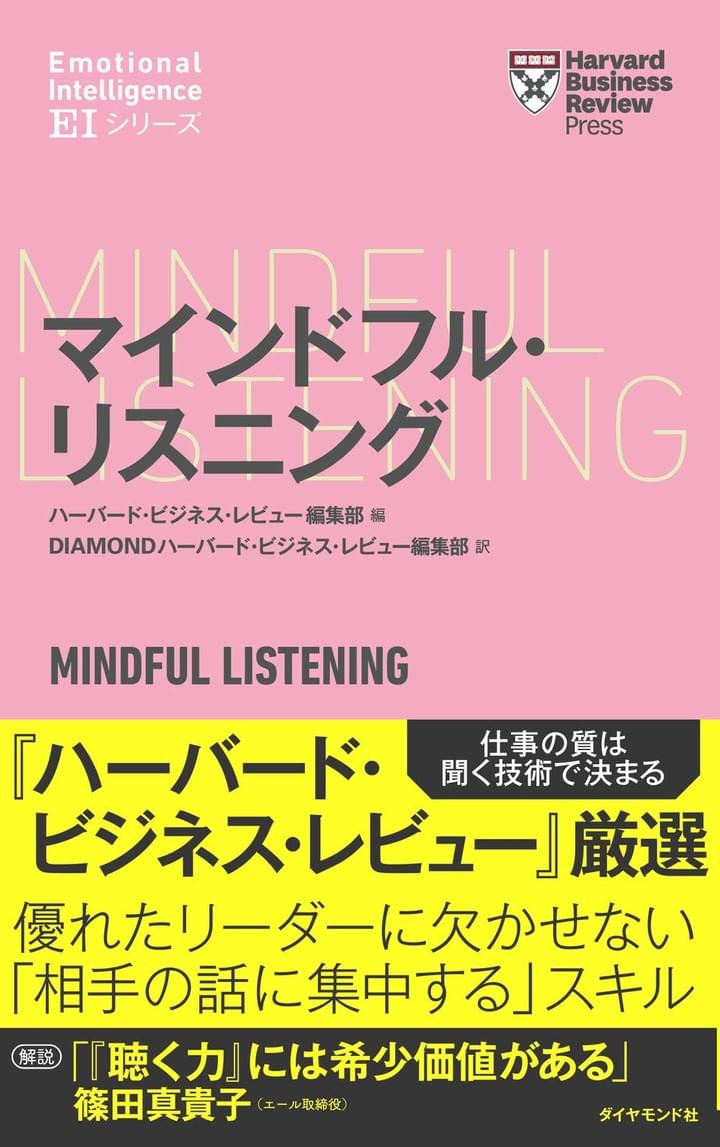5 教育・マネジメント・学修 20冊
※選書リストのすぐ下に詳しい情報と「引用」があります。
👇
1『エブリデイ・ジーニアス』 ピーター・クライン=著
2『こうすれば組織は変えられる!』ピーター・クライン=著
3『どうしてあなたは部下とうまくいかないのか?』堀之内高久=著
4『アイスブレイク入門』今村光章=著
5『天才のノート術』内山雅人=著
6『ぼくが読んだ面白い本・ダメな本 そしてぼくの大量読書術・驚異の速読術』立花隆=著
7『すべては子どもたちの学びのために』原田浩司=著
8『スタンフォード式生き抜く力』星友啓=著
9『学習する自由』カール・ロジャーズ+H.・ジェローム・フライバーグ=著
10『教育の完全自由化宣言!』天外伺朗=著
11『人材は「不良社員」からさがせ』天外伺朗=著
12『非常識経営の夜明け』天外伺朗=著
13『自己満足ではない「徹底的に聞く」技術』赤羽雄二=著
14『あなたの心に聞きなさい』高橋恵=著
15『1兆ドルコーチ』エリック・シュミット+ジョナサン・ローゼンバーグ+アラン・イーグル=著
16『「権力」を握る人の法則』ジェフリー・フェファー=著
17『悪いヤツほど出世する』ジェフリー・フェファー=著
18『ブラック職場があなたを殺す』ジェフリー・フェファー=著
19『やっかいな人のマネジメント』ハーバード・ビジネス・レビュー編集部=編
20『マインドフル・リスニング』ハーバード・ビジネス・レビュー編集部=編
※詳しい情報と「引用」は、今すぐこちらから。
👇
1『エブリデイ・ジーニアス』
ピーター・クライン=著
(フォレスト出版)
「天才」を生み出す新しい学習法
「学校を町で一番楽しいパーティーに」
「明日に延ばせることは、先延ばしにしたほうがよいのです」
「やるべき価値のあることは、下手でもやる価値がある」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/dp/4894511460/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_hj9iEbT9S5KZW
2『こうすれば組織は変えられる!』
ピーター・クライン=著
(フォレスト出版)
「学習する組織」をつくる10ステップ・トレーニング
「"仏"の経営? それとも"鬼"の経営?」
「答えは……"鬼の指導は、確かに効果的。ところが仏の指導はもっといい。一番ダメな会社は、何もマネジメントがないところだね"」
「組織の"音楽"に向き合うこと」
「ステップ10 "ショー"を始めよう!」
「ガイディング・メタファーとしてのドラマ」
「ミニドラマとしてのCM」
「ビジネスのなかのショービジネス」
「ドラマは幕の両側にある」
「ビジネスは舞台だ」
「役者たちはどのように演技の質を維持するのか」
「演出家の役割」
「変化に対応するための演出法」
「自分の役について考えさせる」
「役者と演出家の考えが異なるとき」
「だれもが演出家」
「アドリブの必要性」
「アドリブ能力を養う」
「芸術的側面」
「今日の組織に求められるアドリブの能力は、ジャズのアンサンブルにたとえられる。演奏者たちにはそれぞれ決まった職務(役割と責任)があり、一定の基準と統一ルールが存在する(それがなくては、制御不能な混沌状態に陥ってしまう)」
「すべての演奏者が、音楽のルールに則って演奏しながら、共通の目的を軸に信頼関係を築き上げるとき、結果は極上のものとなる」
「いつまでも創造的でいること」
「時代遅れのショーはいらない」
「ドラマティックな時代をものにする」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/こうすれば組織は変えられる-―「学習する組織」をつくる10ステップ・トレーニング-ピーター-クライン/dp/4894511312/
3『どうしてあなたは部下とうまくいかないのか?』
堀之内高久=著
(フォレスト出版)
「--"ほめる"という行為は、その相手が無能であることが前提になっている」
「部下を"ねぎらう"。"ほめる"のではなく、ねぎらおう。これが本書の大きな提案です」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/どうしてあなたは部下とうまくいかないのか-堀之内-高久/dp/4894511770/
5 教育・マネジメント・学修 20冊
4『アイスブレイク入門』
今村光章=著
(解放出版社)
こころをほぐす出会いのレッスン
「よく知っている仲間どうしであっても、アイスブレイクをすれば、出会いなおしをすることができます」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/dp/4759223428/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_TPYH9DBJ4VRXETK1TM2S
5『天才のノート術』
内山雅人=著
(講談社)
連想が連想を呼ぶマインドマップ®️<内山式>超思考法
「こうしたコミュニケーションの深さは、Seeing(出会いのレベル)、Doing(行動のレベル)、Being(あり方のレベル)と表すこともできるかと思います。また、私は独自に"コンシャスフィア(意識の階層)"というモデルで説明するときもあります。これらは、目に見えているものにとらわれすぎることなく、人やコミュニケーションのあり方や本質をなす、目には見えない深い層を意識していこうとするモデルです」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/dp/4062729040/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_40GPAAAX7AZ7K5TXA92J
6『ぼくが読んだ面白い本・ダメな本 そしてぼくの大量読書術・驚異の速読術』
立花隆=著
(文藝春秋)
「全体の流れとキーワードをつかめ」
「要は、脳の無意識の働きを信頼することである」
「これは音楽的な読み方から、絵画的な読みへの転換と言い変えてもよい」
「この世界は、どんな人間でも処理しきれないほどに情報が氾濫している世界だということがたちどころにわかる。これからの時代、人間が生きるとはどういうことかというと、"生涯、情報の海にひたり、一箇の情報体として、情報の新陳代謝をつづけながら情報的に生きる"ことだということが直観的にのみこめてくる」
「要するに、私がいいたいことは、本は必ずしも、はじめから終わりまで全部読む必要はないということである」
「人間の脳は、正常でないものを素早く見つけるようにプログラムされている」
「本に書いてあるからといって、何でもすぐに信用するな。自分で手にとって、自分で確かめるまで、人のいうことは信じるな。この本も含めて」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/ぼくが読んだ面白い本・ダメな本-そしてぼくの大量読書術・驚異の速読術-立花-隆/dp/4163573100/
5 教育・マネジメント・学修 20冊
7『すべては子どもたちの学びのために』
原田浩司=著
(あめんどう)
不登校、いじめ、勉強嫌いがなくなった学校
「すべての子どもがもつ八つの能力。マルチ知能(Multiple Intelligences)という考えそのものは、アメリカの心理学者ハワード・ガードナー(Howard Gardner)が提唱したものです」
「ガードナーは、一般に行われている知能検査は、知能というものを狭くとらえすぎていると考え、人間には次に挙げる八つの領域の知能(能力)が存在すると指摘しました。そして、どんな人にも、これらの知能が何らかのかたちと程度で備わっていると論じたのです」
「言語的知能--読む・書く・話す能力」
「論理・数学的知能--計算する・数字で考える・筋道を立てて考える能力」
「空間的知能--絵を描いたり形や空間を把握する能力」
「身体・運動的知能--体全体や手先の動きをあやつる能力」
「音楽的知能--メロディを聞き分ける・歌う・演奏する能力」
「対人的知能--人間関係を良好に保つ能力」
「内省的知能--自分を観察し管理する能力」
「博物的知能--自然に親しみ共生する能力」
「学習過程の大胆なとらえ直し」
「算数の授業であっても、使う知能は論理・数学的知能だけではないのです。たとえば"2+3"の足し算をするときに、児童を立たせて二人のグループと三人のグループをつくらせ、移動してグループをくっつけると五人のグループができる、という指導をすれば、身体・運動的知能を使って算数を学んだことになります。つまり、身体・運動的知能を使って論理・数学的知能を高めていくことができるのです」
「自分の能力に気づく子どもたち」
「アームストロングは、これらを平易な言葉に置き換え、子どもたちが好きな食べ物を使って"マルチ知能のピザ(マルチ・ピザ)"」という絵に表しました。A小では、それをポスターにして教室に掲示したり、プリントや下敷きにして配ったりしました」
「ことば。ことばを話したり、聞いたり、読んだり、書いたりする力」
「すうじ。計算する、順番で考えるなど、数字で考える力。きちんと筋道を立てて考える力」
「え。絵や色や形や立体や空間をとらえる力」
「からだをつかう。体全体の大きな動きや、手先の小さな動きをあやつる力。バランスをとる力」
「おんがく。メロディを聞き分けたり、歌ったり、演奏したり、歌をつくったりする力」
「ひと。ほかの人の気持ちを理解したり、表情を読んだり、協力する力」
「じぶん。自分の得意や苦手がわかったり、目標を立ててがんばったり、きもちや行動をコントロールしたり、自分を大切にするなど、自分をみつめる力」
「しぜん。植物や動物などの自然を知ったり、分類したり、世話をしたりする力」
「マルチ・ピザで何が変わったか」
「子どもたちの変化」
「教師の変化」
「日本に発達障害の子どもは何人ぐらいいると思われるでしょうか。文部科学省が二○一二年に行った調査では、通常学級において学習面や行動面で著しい困難を示す児童生徒(つまり発達障害の子ども)の割合は、約六.五%と発表されています。その時点の小中学生の総数である約一○三三万人にこの割合を当てはめると、約六七万人が発達障害ということになります。一クラスの人数を三○〜四○人とすれば、一学級に二〜三人いる計算になります。この調査は客観的なアセスメントによるものではなく、全国から抽出された教師の主観的判断を集計した推定値です。私の経験からは、比率はもっと高いような気がします」
「格差と貧困の再生産」
「児童養護施設と学校が学び合う」
「学校に行けない外国籍児童」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/dp/4900677272/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_31CHG9JG2CMEPZ366R14
8『スタンフォード式生き抜く力』
星友啓=著
(ダイヤモンド社)
「全世界的に猛威を振るうモンスターな人たち」
「"モンスター医師"や"モンスター患者"の話を耳にすることも少なくありません。さらに我々教員を悩ます"モンスターペアレント"や、接客業の人たちを苦しめる"モンスタークレーマー"もたくさんいます」
「"生き抜く力"の3つの基本要素」
「"生き抜く力"をつけるトレーニングは、"生き抜く力"がすでに私たちの潜在能力にあることを自覚することから始まります」
「他人の痛みや体験を自分の脳に映し出す"ミラーニューロン"や利他的な心と身体をつなげる"ベガス神経"など、"生き抜く力"の源泉は私たちのDNAに刻まれているのです」
「1つ目は、"聞き取る力"です」
「この力を高めるために"アクティブ・リスニング"を紹介します」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/dp/4478110662/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_YKWMNT4TTPV8G93YYD8A
9『学習する自由』
カール・ロジャーズ+H.・ジェローム・フライバーグ=著
(コスモスライブラリー)
「校長役の教師」
「大きなアイディアを促進すること」
「集団で解決を見出すこと」
「校長は、(教師の置き換えの手引きに従う)管理者としてではなく、ファシリテーターになったのである」
「ヴィジョンは推進出来るか?」
「最高の指導者は他者がリードするのを許容する」
「彼女(デニー)は、演劇の教師としての自分の経験から、芸術がない学校にいれば生産的な市民にはならなかったであろうと思われる多くの子どもを引き受けることができること、そして……総合芸術の設備……が彼らを多くの仕方で変えるであろうことを知っていました」
「……私たちは、芸術の経験が他者を援助する最上の準備になると分かりました」
「彼らは、資格をもった教師にとって代わるのではなく、その補助をします。豊かにするのです。そのことにより、生徒と教師に専門の世界の新しい考えや経験がつねに送られることになります」
「しかし、最初から、彼女(ルース)のモットーは、……"教育は信頼への冒険である"でした」
「だから、彼女は、音楽の素養と経験をもつ数学の教師、オペラの経験をもつ言語の教師、ピアノと演劇の経験をもつ英語の教師などを雇ったのです、等など」
「私は、英語を教える若い教師を雇ったばかりです。素晴らしい英語の教師であるばかりでなく、彼女はイアーブック(卒業記念集)と新聞をつくります。そして、彼女は、ヒューストン・バレー・アカデミーの授業を受けているのです。だから、ダンスがわかるわけなのです」
「生徒がギャングに加わるとき、彼らは、アイデンティティの源を探している」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/dp/4434085700/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_13D95D476G1G9GB8QW02
5 教育・マネジメント・学修 20冊
10『教育の完全自由化宣言!』
天外伺朗=著
(飛鳥新社)
子どもたちを救う七つの提言
人間性教育学シリーズ1
「集中が妨げられずに作業が完遂できると、子どもは深い満足感が得られ、劇的に態度が変わる。これを"正常化"という」
「子どもがみんな"正常化"を達成すると、先生は不要になる」
「子どもに指示・命令をすることは御法度。同様に、間違いを訂正することも、ほめることも集中の妨害になる」
「子どもは、集中に達すると"内発的動機"が満足するまで、何度でも同じ作業を繰り返す。その途中で妨害が入ると、子どもは意識的に悪いことをしてウップンをはらす。それがたびたび起きると、行儀が悪く、気まぐれで、不注意で、ふきげんな子どもが育つ。それに対して罰則で対処すると、非行少年・少女が生まれる」
「大人であっても、決断力や忍耐力が欠如していたり、怠惰、優柔不断な性格で、恐怖や不安を抱いている人は、子ども時代にひんぱんに集中の妨害を受けてきた可能性が高い」
「子どもは、自らの内側に自らを成長・発達させ、自己形成を遂げようとする強烈な力と衝動を秘めている」
「教育とは教えることではない。子どもたちの生命に対する援助だ」
「学校は人間の精神にとって、"死人の家"だ」
「学校は子どもたちに"劣等感"を植えつけてしまう」
「学校は生徒の恐怖心を養い、支配しようとしている。これはとても危険であり、知性はもはや開発、開花、成熟しなくなる。私たちは"独裁政治下と奴隷状態に置かれているこのような子どもたちを救いだそうではないか"と叫ばなければいけない」
「どう考えても、モンテッソーリの学校教育批判は、そっくりそのまま今日の日本の教育システムにあてはまり、そのために子どもたちは悲鳴を上げ、不登校やひきこもりやいじめが激増しているように私には見える」
「私が、確信を持ってこのことを語れるのは、まったく同じ現象が企業の中にも見られ、それを四二年間にわたって観察してきたからだ」
「私自身、CDやNEWSのプロジェクトを立ち上げるとき、マネジメントに反抗して"不良社員"化している"人材"を発掘して中心人物に起用し、"燃える集団"を実現してきた。その時の"不良社員"たちは、成功体験を経て、いまやソニーの中枢をになっている。私が不登校やひきこもりになる子どもたちは、進化した人類だ、とあちこちで発言して、物議を醸しているが、決して観念論を述べているのではなく、以上の体験に根ざしている」
「しかしながら、まともに育ってきた子どもは、とても耐えられないだろう。不登校かひきこもりか、さもなくばいじめにより精神の安定をはからざるをえなくなるだろう。企業だったら上司に反抗的な不良社員になる。だから、日本の社会で、不登校やひきこもりやいじめやニートやフリーターが激増しているのは、本当は喜ばしい現象なのだと思う。それだけ、まともな子どもたちが増えてきたのだ。その中から、次の社会のリーダーが育っていくと確信している」
「教育は芸術だ。知識や技能を教え込むのではなく、単に知能を伸ばすのでもなく、子どものそれぞれの発育段階に応じた"心の糧"を与え、次の発育段階の準備をサポートすることだ」
「日本はいつの間にか、年間三万人を超える自殺大国になってしまった。ディープ・グラウンディングの教育は、いまの日本にとって急務だと、私は考えている。先に述べたように、ディープ・グラウンディングの教育には"創造"が効果的だ。宇宙の創造のお手伝い(農業、園芸など)でもいいし、何もないところから自ら工夫して何かを創り上げる(工作、服飾品の制作、手芸など)のも、ダンス、音楽、絵画、彫刻、詩や散文の創作などもいい」
「ただ、注意しなければいけないのは、自ら考え、自ら工夫し、自ら間違いを発見し、自ら評価することによって、ディープ・グラウンディングが育つことだ。大人がいらぬ口出しをすることで、すべてがぶちこわしになる。間違いを指摘すること、おせっかいなアドバイス、感心したりほめたりすることなどが、すべて御法度なのだ。大人や教師は、無言で温かく見守り、子どもが困って聞いてきたときだけ対応すればよい」
「学校には、叙事文と命令文はあるが、感嘆文がない!」
「集団の中に埋没できないからこそ、不登校になるのだ。要領よく自我を抑圧できず、"自分を持っている"からこそ、苦しんでしまうのだ」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/dp/4870318350/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_PEDZEDFA0X8BDEDC9ZKM
11『人材は「不良社員」からさがせ』
天外伺朗=著
(講談社)
奇跡を生む「燃える集団」の秘密
「……問題なのは、むしろ失敗したとき、もしくは失敗しそうなときです。良い子たちはいち早く安全圏に身を置きますからネ。トップの姿勢や失敗の影にはものすごく敏感です。その引き際の早さは目を見張るほどです。トップがプロジェクトの先行きに不安になったとたん、そのプロジェクトの悪い点をどんどんトップに報告に行きます。--私は最初から反対だったんですけど--といって、昨日までの自分の発言を否定してしまいます」
「スケープゴートにされた人材は、多くの場合、不良社員に化けるか、もしくは不良社員というレッテルが貼られています。だから人材をさがすときには、過去にスケープゴートにされた人に当たると、確率が高いのですよ……」
「その組織の目的が戦争をすることだったら、本当に必要なのは戦上手の武士のはずです。ところが、サロン化している組織では、そのかけがえのない武士を不良社員というレッテルを貼って追い出してしまうのですよ」
「人材は修羅場で育ちます。それも成功する修羅場でのみ育ちます」
「感情的抗争がなければ、会議は和気あいあいになり、ジョークがポンポンと飛び交うようになる。人々は保身に気を使うこともなく、リラックスしてアイディアも出るし、物事を能動的に進めていける。何よりもこだわりがないため、物事の本質は何かというところにみなの意識が向かうことができる」
「過去にも未来にも逃げない」
「専門を分散させる」
「"人材"のひとつの定義は、"内発的動機"の声がちゃんと聞こえる人、逆に"良い子"は"外発的動機"だけで行動する人、ともいえる。成果主義を導入した会社がおかしくなるケースが多いが、"外発的動機"を前面に押し出すことで、誰も"フロー"に入れなくなり、"良い子"ばかりが張り切って、"人材"が駆逐されてしまうことが"フロー理論"から解き明かせる」
「机に座って、鉛筆ナメナメつくった戦略は、まずクソの役にも立ちまへん」
「……だいたい、生きた戦略というのは、必ずしも言葉で表現できるものではないですし、紙の上にも書けないのです」
「戦略というのは、成功のためのシナリオと思えばいいでしょう。ただし、ドラマのシナリオと違うところは、相手のせりふは書けないことです」
「じっと机に座って考えるような戦略家は、まず偽物です」
「D博士によれば、本物の、生きた情報は、他人より速く行動する人のところに、ひとりでに集まってくるという。どういう原理なのかよくはわからないが、行動のスピードと情報の吸引力は正比例するという」
「つまり、生きた戦略というのは、固定したものではなく、速いスピードの行動とともに融通無礙に変化するのです。情況に応じて、やり方を変え、方向を変え、つぎに何をやればよいかに全身全霊を傾けるわけです。心を空しくしてです。したがって、本物の生きた戦略というのは、概略の方向性に加えて、むしろ姿勢とか、心構えとかいってもいいくらいです」
「机に座って考えても、文献を読んでも、インタビューに行っても(なかなか本音は聞けないので)、どうせ腐った情報しか集まらない。それより手近な目標を攻撃するほうが、よほど戦略を練るのに役に立つという論理らしい。手近な目標を短期間に攻めて、成功したなら、今度はそこまで駒を進めて、新たな展開をはかる、という方法論のようだ」
「世の中のトレンドを見切る」
「ビッグ・プロジェクトは危険」
「戦争ならゲリラ戦、企業ならベンチャーの戦い方だ。ゲリラは"フロー"で戦う。武器も人数も圧倒的に劣るゲリラが、なぜ大軍を翻弄できるかというと、"燃える集団"になるからだ。"燃える集団"になり切れなかったゲリラは、あっという間に戦力的に優位な正規軍に殲滅される」
「トップが反対する中でも、成功への"運"をつかんでいく"燃える集団"の偉力を信じることができれば、突破する可能性が高まる。嘆いていると、その"運"は逃げていく」
「"人材"は管理を嫌う。指示・命令されても活きない。おとなしく鎖につながれて、ご主人に尻尾を振る飼い犬ではなく、野原を自由に駆け回る狼なのだ」
「よくしつけられた猟犬なら、ご主人の狩りの役に立つだろう。でもその犬は、本来の野性の発揮は抑えられ、能力は殺され、ひたすら従順に行動するようにしつけられている。従来の企業経営は、従業員をそういうふうにしつけてきた。経営者が優秀なら、それでも業績が上がった」
「狼も集団で狩りをする。でもそれは、誰かの指示のもとに動くのではなく、一匹一匹が最大限に野性の本能を発揮し、集団の中における自らの役割を把握し、結果的に一糸乱れぬチームワークを発揮していく」
「野性の本能を発揮している状態が"フロー"であり、最近では"フロー経営"という言葉も定着してきた。従業員を鎖につないだら、誰も"フロー"には入れない」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/人材は「不良社員」からさがせ-奇跡を生む「燃える集団」の秘密-講談社-α文庫-天外/dp/4062814498/
12『非常識経営の夜明け』
天外伺朗=著
(講談社)
燃える「フロー」型組織が奇跡を生む
人間性経営学シリーズ2
「どうせダメなら楽しく!」
「本質は"アホ"に宿る」
「死は変容のチャンス」
「10章で、ピラミッド型組織を上りつめていき、支配する部下の数が増えると、あたかも自分が成長したかのごとき錯覚を呼ぶという話を書いた。これは、人間なら誰しもが陥る罠であり、本来なら自我が希薄になることにより、逆に自分自身が拡がり、宇宙と一体化の方向に向かうのが正常な意識の成長・進化なのに対し、自我を強固に保持したままで拡大しようとあがいているのだ。結果として、自我の肥大という病理的な症状を示す人が、社会の指導層に多い」
「もうひとつの問題点は、ペーパーテストで大脳新皮質ばかりを鍛えて、大脳辺縁系の働きがきわめて弱い人が指導層に多いことだ。そういう人は、やたらに言語能力が高く論理にも強いが、タオが見えず、現実のドロドロした問題にしっかりと対処することができない」
「いまの心理学は、社会に適応できていれば健康とみなしてしまうので、このような指導層に蔓延する病理的症状を記述する用語がない。そこで、その病理的な傾向を脱した状態を"ディープ・グラウンディング"と呼ぶことにしたのだ」
「そして、首尾よく徹底的に情動を抑圧している鈍感な人を"沈着冷静で優秀なリーダー"として重用するのだ」
「情動や身体性を統合し、深いレベルの本質的な自分自身に接地し、自分は本当に何を感じ、何を求めているかが実感できるようになると、人は絶対的な存在感の確立の方向に進んでいける。それが"ディープ・グラウンディング"だ」
「シャドーのプロジェクションが強く、戦いのモードにあるとき、人はディープ・グラウンディングの方向にはなかなか進めない。いまの社会の指導者層は、そういう人たちで満ち満ちている」
「それでは、どこに行けばディープ・グラウンディングに達した人に会えるかというと、一芸を極めた職人さん、お百姓さん、あるいはアーティストの中には結構多い。そういう目で身の回りを見れば、自分の仕事に対して誇りを持ち、どっしりとしたゆるぎない自信があり、かといって自己顕示欲があまり強くない人が何人か見つかるのではなかろうか」
「じつは、ディープ・グラウンディングに向かうためには、他人の目、社会の評価などはマイナスの作用をする。相対的な評価に依存する習慣を身につけてしまうからだ。物や農作物に真剣に相対したとき、人は相対的な評価を超えることができる。そこには、宇宙の評価としかいいようがない境地があるのだ」
「一般の教育で、とても大切と考えられている"ほめる"という行為は、ディープ・グラウンディング教育ではご法度だ。前述のように、他人の評価に依存させてしまうからだ」
「前に情動や身体性に接地する、と述べたが、それは古い脳を鍛えることにほかならない。近代文明人は、ほぼ全員、情動や身体性を切り離した状態で生きているのだが、誰もそれに気づいていない。皆がそうなので、おかしいと思わないのだ。ただ、演技のトレーニングをしてきた俳優さんたちは、情動に接地することを学んできている。また、スポーツに命をかけて入れ込んできた人たちは、身体性に接地することを体験してきている」
「物を創ることもなく、演技の勉強もせず、スポーツもせず、お勉強ばかりしてきて、論理と言語の虚構の中だけで生きてきた人たちは絶望的だ」
「じつは人は、病気になると否が応でも死と直面するため、意識の変容を起こしやすくなる。それを医療者が密かにサポートするのだ。つまり、従来の病院のように、病気が治って元の生活に戻ればよし、とするのではなく、せっかく病気になったのだから、元より一段と高い境地に着地することを目的とする」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/非常識経営の夜明け-燃える「フロー」型組織が奇跡を生む-人間性経営学シリーズ2-天外-伺朗/dp/4062149850/
5 教育・マネジメント・学修 20冊
13『自己満足ではない「徹底的に聞く」技術』
赤羽雄二=著
(日本実業出版社)
「アクティブリスニングができる人が1人増えると、周囲の5人以上が幸せになると考えています。その方々がまた周囲の5人以上を幸せにすると、あっという間に何万人も何十万人もアクティブリスニングをするようになり、幸せになっていきます」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/dp/4534057997/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_KCX6H793K3Y0QM76FM9M
14『あなたの心に聞きなさい』
高橋恵=著
(すばる舎)
「大きな悲しみを抱えた人がいても同情しない、同調はしない。ただ聞くだけで救いになる」
3歳で父が戦死、40歳で離婚、42歳で二人の娘を育てながら、後に日本一となるPR会社サニーサイドアップを創業した高橋恵さん。
70歳を過ぎて一般社団法人おせっかい協会を設立し、働く女性のメンターとして「心のままに生きる」秘訣を教えてくれます。
『いくつであっても女性らしく生きる』あなたにお薦めの書籍です。
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/dp/4799108301/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_MaijEbKBD7TAM
15『1兆ドルコーチ』
エリック・シュミット+ジョナサン・ローゼンバーグ+アラン・イーグル=著
(ダイヤモンド社)
シリコンバレーのレジェンド ビル・キャンベルの成功の教え
「人がすべて」
「あらゆるマネージャーの最優先課題は、部下のしあわせと成功だ」
「"旅の報告"から始める」
「円卓の"背後"に控える」
「"天才"とうまく付き合う」
「プロダクトがすべてに優先する」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/dp/4478107246/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_JLfaGbEWTGXZT
5 教育・マネジメント・学修 20冊
16『「権力」を握る人の法則』
ジェフリー・フェファー=著
(日本経済新聞出版社)
「"権力"を手にするための七つの資質」
「決意」
「エネルギー」
「集中」
「自己省察」
「自信」
「共感力」
「闘争心」
「職場でのいわゆるパワーハラスメントを取り上げた著作や実証研究は数多い。いずれも、暴言や罵詈雑言の類が、標的になった社員にとってはもちろん、職場にとってもいかに有害かを指摘している。ところがこうした行為が一向にやむ気配がないのは、どうしたわけだろうか。答えは簡単、加害者側にとってはこれほど有効な手段はないからである」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/dp/4532197147/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_SDGMCDRKYCWFGAX6Q7XZ
17『悪いヤツほど出世する』
ジェフリー・フェファー=著
(日本経済新聞出版社)
「嘘つき、裏切り、自己中心…これが、リーダーの"資質"だ」
「リーダー教育産業の失敗」
「熱心にリーダー研修を受けた人ほど危険」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/dp/4532198550/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_VWTDPGA679GMYR4F3JAX
18『ブラック職場があなたを殺す』
ジェフリー・フェファー=著
(日本経済新聞出版社)
「職場のストレス要因の多くは受動喫煙と同じぐらい有害である」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/dp/453232274X/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_4SfaGb3K2ZXK0
19『やっかいな人のマネジメント』
ハーバード・ビジネス・レビュー編集部=編
(ダイヤモンド社)
ハーバード・ビジネス・レビュー[EIシリーズ]
「繰り返しになるが、これからの時代、良くも悪くも、日本のビジネスで"面倒くさい人との付き合い方"はさらに重要になってくるだろう」
「ケーススタディ1:職場にとどまったため、被害を受け続ける」
「ケーススタディ2:悪しき振る舞いに抗議する」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/dp/4478106010/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_EXV3ZQK8RK1PB8JW6SA8
20『マインドフル・リスニング』
ハーバード・ビジネス・レビュー編集部=編
(ダイヤモンド社)
ハーバード・ビジネス・レビュー[EIシリーズ]
「職場の潤滑油となる貴重な存在"ヒーリング・リーダー"」
続きは、今すぐこちらから。
👇
https://www.amazon.co.jp/dp/4478111693/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_40C94F3PQBZSQRA3XRCS